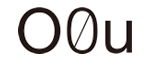
WEB STOREサービス終了のお知らせ
平素よりO0uを
ご利用いただきまして
誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、
O0uウェブストアすべてのサービスの提供を
終了させていただくこととなりました。
急なお知らせになりましたことをお詫びすると共に
ご愛顧いただきましたことを
心より御礼申し上げます。
=========================
ご利用いただきまして
誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、
O0uウェブストアすべてのサービスの提供を
終了させていただくこととなりました。
急なお知らせになりましたことをお詫びすると共に
ご愛顧いただきましたことを
心より御礼申し上げます。
〈 メールマガジン配信設定について 〉
O0u and STからのお知らせは、
2025年2月4日(火)をもって配信停止となりました。
現在、O0uからのお知らせを
受信されている会員様につきまして
and ST(アンドエスティ)からのお知らせの受信を
ご希望されない会員様は
マイページ内の「会員情報の変更」より
「メールで受け取る」「アプリで受け取る」の
チェックを
はずしていただきますよう
お願いいたします。
お客様には大変お手数をお掛けしますが、
何卒よろしくお願いいたします。
ご登録情報の変更はこちらから ❯
O0u and STからのお知らせは、
2025年2月4日(火)をもって配信停止となりました。
現在、O0uからのお知らせを
受信されている会員様につきまして
and ST(アンドエスティ)からのお知らせの受信を
ご希望されない会員様は
マイページ内の「会員情報の変更」より
「メールで受け取る」「アプリで受け取る」の
チェックを
はずしていただきますよう
お願いいたします。
お客様には大変お手数をお掛けしますが、
何卒よろしくお願いいたします。
ご登録情報の変更はこちらから ❯
※※ご注意※※
上記お手続きを完了していない会員様につきましては
and ST(アンドエスティ)からのお知らせが
配信されますので予めご了承くださいませ。
他ブランドからのお知らせ受信をご希望の会員様は、
上記お手続きは不要となります。
急なお知らせになりましたことをお詫びしますと共に
O0uをご愛顧いただき
誠にありがとうございました。
スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
今後ともand ST(アンドエスティ)を
よろしくお願いいたします。
2025年2月4日
and ST(アンドエスティ)
o0u.com(公式ブランドストア)
O0uをご愛顧いただき
誠にありがとうございました。
スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
今後ともand ST(アンドエスティ)を
よろしくお願いいたします。
2025年2月4日
and ST(アンドエスティ)
o0u.com(公式ブランドストア)